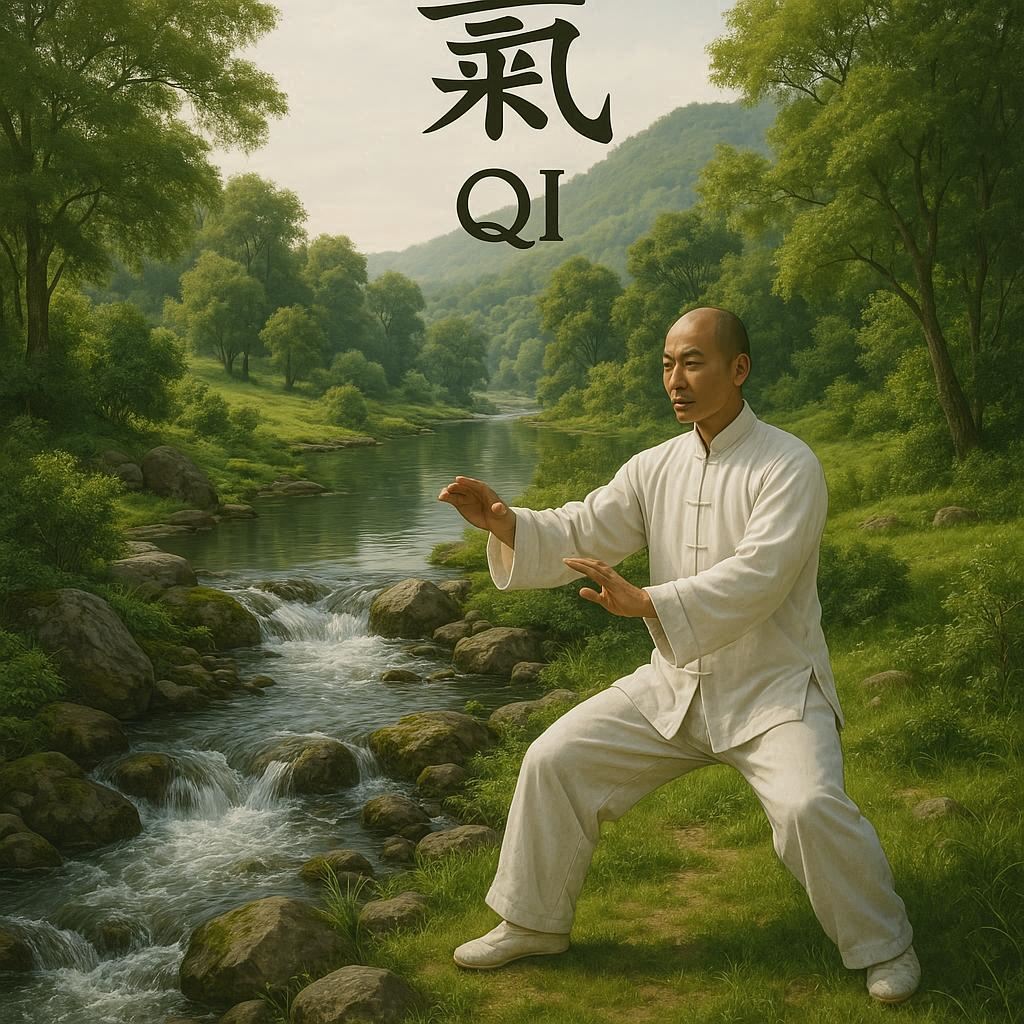東洋医学の基本 気 とは?不足・滞りが招く不調と、体の巡りを整える方法につてい紹介します。東洋医学の根幹をなす「気」の概念と、それが乱れたときの不調、そしてご自身でできる巡りの整え方について解説します。
東洋医学において、「気」は、私たちの心身の活動すべてを支える、目に見えない生命エネルギーの源です。現代医学でいう「代謝」や「免疫力」「活力」といった概念を包括する、非常に重要な要素です。「元気」「病気」「気力」といった言葉に「気」が使われているのは、まさにその働きが深く関わっているからです。
東洋医学の基本 気 とは?
「元気」「やる気」「病気」など、私たちは日常的に「気」という言葉を使いますが、東洋医学において「気」は単なる気分や雰囲気ではありません。それは、私たちの生命活動すべてを支える、目に見えない根源的なエネルギーです。
体の成長、血液の循環、体温の維持、病気への抵抗力—。これらの働きはすべて、この「気」の力によって推し進められています。
あなたの疲れやすさやイライラ、体のだるさは、この大切な「気」が不足したり、体内で滞っていたりするサインかもしれません。
本記事では、東洋医学でいう「気」の役割を深く理解し、あなたの体質が「気虚(ききょ)」と「気滞(きたい)」のどちらに傾いているのかを解説。そして、日々の生活の中で誰でもできる体の巡りを整える方法をご紹介します。
1. 「気」の主な5つの働きと役割
気が体内をスムーズに巡り、量も充実していることで、私たちの健康は維持されます。気には主に次の5つの重要な役割があります。
| 働き | 意味 | 具体的な作用 |
| ① 推動作用(すいどうさよう) | 押し動かす力 | 血液や体液の循環、内臓の活動、成長・発育を促すエネルギー源。 |
| ② 温煦作用(おんくさよう) | 温める力 | 体温を一定に保つ働き。内臓を温め、機能が円滑に働くのを助けます。 |
| ③ 防御作用(ぼうぎょさよう) | 守る力 | 現代医学でいう免疫機能・抵抗力。外からのウイルスや細菌(外邪)の侵入を防ぎます。 |
| ④ 固摂作用(こせつさよう) | 保持する力 | 体に必要なもの(血、汗、尿など)が漏れ出ないように体内に留める働き。 |
| ⑤ 気化作用(きかさよう) | 変化させる力 | 飲食物を消化・吸収して「気」や「血」「水」に変換する代謝機能。 |
3. 体の「気」の巡りを整えるためのセルフケア
「気」は、私たちが普段の生活で得る「後天の気」(飲食物と呼吸から得られるエネルギー)によって補われます。日々の養生で「気を補い」「気の流れを良くする」ことが大切です。
気虚(不足)を改善するための養生法
気を補うには、消化吸収を助け、無理なくエネルギーを蓄えることが重要です。
- 食事で「気を補う」:
- 消化に良い温かいもの:お粥、うどん、スープ、味噌汁などを意識的に摂る。
- おすすめ食材:山芋、かぼちゃ、豆類(大豆、いんげん豆)、鶏肉、牛肉、うなぎなど(胃腸の働きを助け、気を補う食材)。
- ポイント:冷たいものや生ものの摂りすぎは胃腸の働きを弱らせ、気を作る力を低下させるため控えましょう。
- 休養と睡眠:
- 無理な運動は気を消耗させるため避け、質の高い睡眠と休養をしっかり取る。
- 汗をかきすぎる激しい運動や長時間のサウナは控えめにし、疲れない程度のウォーキングやストレッチを行う。
気滞(滞り)を改善するための養生法
気の流れを良くするには、リラックスと発散がカギとなります。
- 食事で「巡りを良くする」:
- 香りの良い食材:香りは気の巡りを良くするとされています。柑橘類(みかん、ゆず)、ミント、春菊、しそ、セロリ、ジャスミン茶などを積極的に摂る。
- その他:玉ねぎ、らっきょうなどの香味野菜も効果的です。
- 呼吸と運動:
- 深呼吸: 溜まった気を吐き出すイメージで、呼気(吐く息)を意識してゆっくり深呼吸を繰り返す。
- 適度な発散: ストレス解消のため、軽めのジョギングやヨガ、ストレッチなど、気分転換になる運動を習慣にする。
- リラックス: ぬるめのお風呂にゆっくり浸かり、心身の緊張を解きほぐしましょう。
「気」のバランスを意識することは、体調を管理するための羅針盤となります。ご自身の体の声に耳を傾け、食事や休養、運動でその巡りを整えることが、東洋医学的な健康への第一歩です。
実例「気の流れ」を改善して うつ病を克服 東洋医学 (漢方)の治療とは