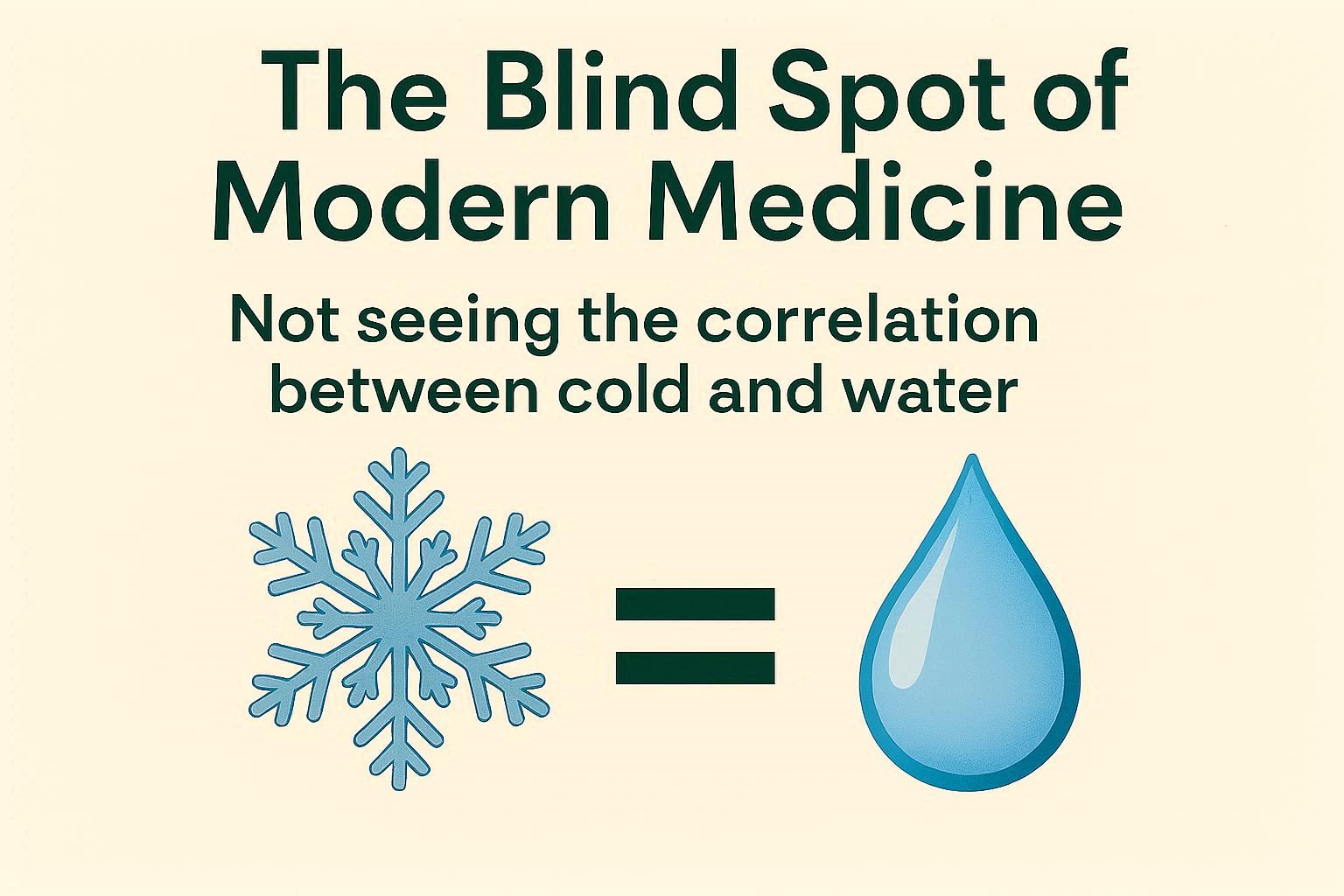現代医学の盲点 冷えと水 の相関関係を見ていないからです。冷え性やむくみは、多くの人が抱える慢性的な不調です。しかし、現代西洋医学が個別の症状として捉えがちな一方で、東洋医学(漢方)の世界では、これらの不調を「水(すい)」の代謝異常、すなわち「水毒(水滞)」と深く結びつけて考えます。
「現代医学の盲点」という点は、東洋医学(特に漢方)の考え方と現代西洋医学の視点の違いをよく表しています。
冷え性やむくみは、多くの人が抱える慢性的な不調です。しかし、現代西洋医学が個別の症状として捉えがちな一方で、東洋医学(漢方)の世界では、これらの不調を「水(すい)」の代謝異常、すなわち「水毒(水滞)」と深く結びつけて考えます。
「冷え」と「水(水分代謝)」の相関関係は、東洋医学では非常に重要な概念ですが、現代西洋医学では個別の症状として扱われることが多く、「盲点」と感じられることがあります。
冷えと水 の相関関係を見ていない
1. 東洋医学(漢方)の視点:「水毒(水滞)」と「冷え」
東洋医学では、人の体を構成する基本要素として「気・血・水(き・けつ・すい)」の三つが過不足なく滞りなく巡っている状態が健康とされます。
- 「水」:血液以外の体液、リンパ液、消化液など、体内のすべての水分を指します。
- 「水滞(すいたい)」または「水毒(すいどく)」:体内の水分が滞ったり、過剰になったり、偏ったりして調和が取れない状態を指します。
この「水毒」の状態は、「冷え」を招く主要な原因の一つと考えられています。
冷えと水毒のメカニズム(東洋医学的解釈)
- 水分代謝の低下 → 停滞水の増加:
- 体が冷える(「気」の不足や停滞も関わる)と、胃腸や腎臓の機能が低下し、水分を適切に排泄・代謝する力が弱まります。
- 体内に不要な余分な水分が溜まり、むくみや水毒を引き起こします。
- 停滞水の「冷え」を増幅:
- 溜まった余分な水は、体温で温まりにくく、熱を持たない「冷たい水」として存在します。
- 特に下半身に溜まると、その部分の冷えを強め、「冷えのしつこさ」につながります。
- 悪循環:
- 体温の熱が冷たい水に奪われやすくなり、体はさらに冷え、代謝はさらに悪化する悪循環に陥ります。
漢方では、むくみや冷え、めまい、頭痛、鼻水など、水分代謝の異常に関わる症状に対して、「当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)」や「真武湯(しんぶとう)」のように、温めながら水分代謝を整える処方が用いられます。
2. 現代西洋医学の視点
現代西洋医学では、臓器や細胞レベルでの病態生理学に基づき症状を捉えます。
- 冷え:末梢血管の収縮、血流障害、自律神経の乱れ、ホルモンバランスの異常などとして説明されます。
- むくみ(水滞):心臓、腎臓、肝臓などの臓器機能の低下、静脈・リンパ管の鬱滞、低アルブミン血症など、具体的な病態や検査値に基づいて診断・治療されます。
体内の水分量は血液検査や尿検査で把握されますが、冷えを訴える多くの患者は検査値に異常が出ないため、「水分代謝の軽微な滞り」や「冷たい水が体内に溜まっていること」が冷えの主因として治療のターゲットになりにくい傾向があります。
つまり、現代医学は病的なむくみは扱いますが、「病気ではないが体調不良を引き起こす軽度の水滞」と「冷え」の複合的な関係には、東洋医学ほど深く注目していません。
この「水」と「冷え」の相関関係に注目することは、未病(病気ではないが不調な状態)を改善し、免疫力を高めるための重要なヒントとなります。
「何となくスッキリしない」「体の流れがよどんでいるようだ」と感じる人の中には、その原因が「水」にある場合も多いです。脳血栓や心筋梗塞など、血栓症による死亡者は毎年30万人にのぼり、日本人の死因の2位、3位を占めています。そのため、西洋医学を中心に「水分をとるように」と健康指導が行われることが多いです。
人体の60~65%は水分でできており、体内のすべての化学反応は水が関与して行われています。そのため、水の重要性は言うまでもありません。水のないところに生命は存在できないのです。しかし、「過ぎたるは及ばざるがごとし」で、体内に水が多すぎると、さまざまな害が生じます。
植木に水をかけないと枯れますが、かけすぎると根が腐ります。例えどおり、水も私たちの体外の水分が多い状態=高湿度では、不快指数として心身の不快感が表れます。つまり、水には諸刃の剣的な一面があるのです。
よく子供が寝冷えすると下痢(水様便)(冷→水)を起こしますし、冷房に入ると頭痛や腹痛(冷→痛)を訴えることもあります。雨(水)が降ると神経痛やリウマチの痛み(水→痛)が悪化することもよくあります。また、雨に濡れると体が冷える(水→冷)ことは、誰でも経験があるでしょう。このように、「冷・水・痛」は互いに関係しています。どんな健康な人でも、冬山で遭難すると外傷を負わなくても、冷えのために命を落とすことがあります。つまり、人間は冷えると危険なのです。
こうした特殊な事情を除くと、本当に健康な人は病気になりません。風邪でも、がんでも心臓病でも、精神疾患でも、病気は健康から少し死に近い位置にあります。つまり、冷えると病気になりやすく、死に近づく理屈になります。そのため、冬は風邪、脳卒中、心筋梗塞をはじめ、がんや膠原病、胃腸病など、ほとんどの病気で死亡率が高くなります。
風邪は万病のもとと言われますが、英語では「cold(冷え)」です。つまり、「冷えは万病のもと」と言えるのです。
人間は、「赤ちゃん」という体温が高く、赤血球が多い多血症の状態で生まれ、年齢とともに白髪になり、白内障を患い、皮膚に白斑が生じるなど、体全体が白っぽくなる「白」の状態で老化・死亡していきます。「白」は雪の色のように冷える色です。冷蔵庫に食べ物を入れると硬くなるように、水も冷やすと氷になるように、宇宙の物体は人間の体も含め、冷えると硬くなります。
そのため、体温の高い赤ん坊の肌はマシュマロのように柔らかいですが、老人の肌はカサカサと硬くなります。若い人の立ち居振る舞いはしなやかですが、老人のそれは硬くぎこちなくなります。筋肉や骨の体温が低いためです。体の表面(骨・筋・皮膚)の体温が低いのに、内臓の体温だけが高いことはあり得ないため、内臓も硬くなる症状が現れてきます。
これが動脈硬化、心筋梗塞・脳梗塞、がんです。がんは「やまいだれ」の中に「岳=岩」がある字で、硬い病気であることを表しています。ある意味、がんは冷えの病気でもあります。そのため、甲状腺の働きが活発になり新陳代謝が良くなるバセドウ病の人は、発熱や下痢が起こりますが、発がん率は一般の人の1000分の1以下です。
実験では、がん細胞と正常細胞を培養して温度を上げると、正常細胞は43度まで生きられますが、がん細胞は39.6度を超えると死滅します。自然治癒したがん患者は、肺炎や丹毒にかかり、発熱していたことが多いのです。がん細胞は熱に弱いのです。
人間の体にはどこにでもがんができますが、心臓がんや脾臓がんはほとんど聞きません。心臓は四六時中働き続け、発熱量の多い臓器だからです。肺臓も赤血球が集まり体温が高いため、がんが発生しにくいと考えられます。
逆に、発がん性の高い臓器は、肺、食道、胃、大腸、子宮など、外界とつながる管腔臓器です。これらは体温が低くなりやすく、乳房も体幹から突出しているため体温が下がりやすく、乳がんが発生しやすいと考えられます。
女性に多い強皮症、SLE、シューグレン症候群などの膠原病も、皮膚や内臓が硬くなる病気であり、ある面では冷えの病気です。自己免疫病とされるクローン病も腸管が鉛のように硬くなるため、冷えの病気と考えられます。うつ病や自殺も体温の低い人に起こりやすく、北欧や北日本で多いことを考えると冷えと関係しています。痛風も足先(体温27~28度)の冷えた部位で尿酸が固まって起こるため、冷えの病気です。高脂血症や高血糖(糖尿病)も、血液内の脂肪や糖分が十分に燃焼できずに溜まるため、やはり冷えと関係しています。脂肪や糖分は体温が高ければ燃焼されます。
病気は必ず血行の悪い部分に起こります。血液は水、酸素、栄養、白血球、免疫物質を全身に運んでいるからです。血行の悪い部分、つまり冷えた部分には病気が発生しやすいのです。
そのため、腹痛のときには腹に手を当て、頭痛のときには頭に手を当てます。これが「お手当て」であり、治療の第一歩です。手を当てて血行を良くして温め、栄養と免疫物質の供給を増やすことで、自然に治癒を促す知恵なのです。