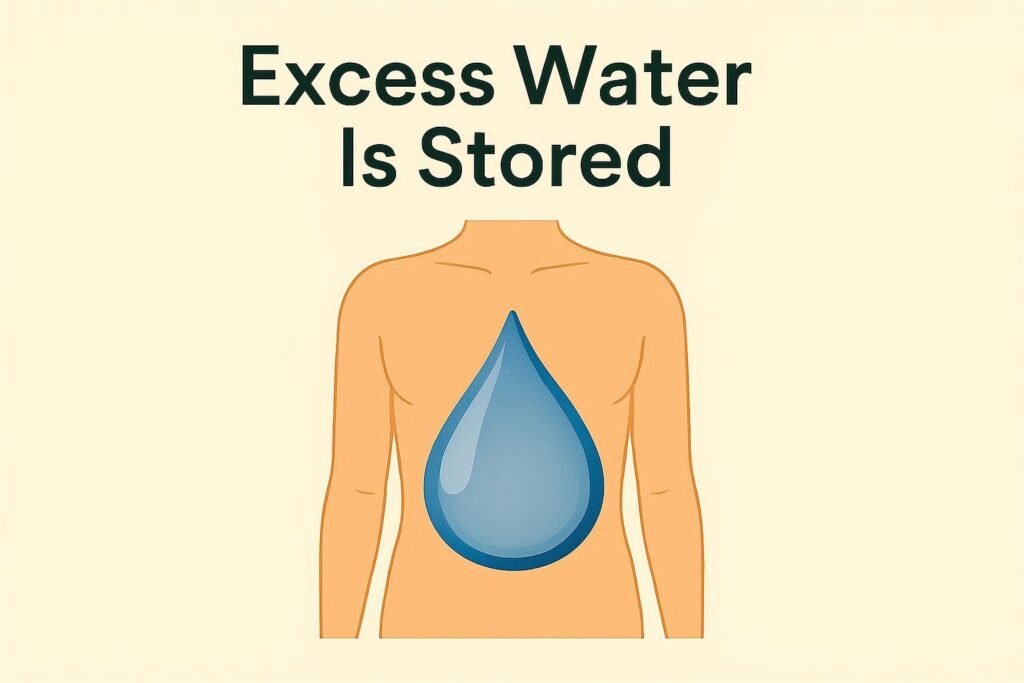現代人は、知らず知らずのうちに 余分な水をため込んでしまっていることが多々見られます。うつ病やうつ的状態に陥ると、何となく体がだるい、動きたくない、やる気がない…などの精神症状にプラスして、食欲がなくなる、便秘する、尿の出が悪くなる…などの身体症状も出現することが増えます。
余分な水をため込んでしまっている
気づかないうちに体に余分な水をため込んでしまう状態は、東洋医学で「水滞(すいたい)や水毒(すいどく)」と呼ばれ、冷えやだるさ、むくみなど、さまざまな不調の元凶となります。
現代の生活習慣は、この「水滞」を引き起こしやすい要素に溢れています。余分な水をため込んでしまう主な原因と、その対策を見ていきましょう。
余分な水をため込む3つの大きな原因
水滞は「水の摂りすぎ」だけでなく、「水の排出・巡りの悪さ」によって引き起こされます。
1. 体を冷やす習慣が代謝を止める
体内に余分な水が溜まる最大の原因の一つが「冷え」です。
-
冷たい飲食: 氷入りの飲み物や冷たい食べ物は、胃腸(東洋医学でいう「脾」)を直接冷やします。胃腸の働きが弱まると、水分を適切に吸収・排泄する能力(水分代謝)が鈍り、水が溜まりやすくなります。
-
血行不良: 体が冷えると血管が収縮し、血液とリンパ液の巡りが悪化。水分がスムーズに回収されず、細胞間に漏れ出てむくみとなります。溜まった水は熱を持たないため、さらに体を冷やすという悪循環を生みます。
2. 運動不足によるポンプ機能の低下
水分を全身に巡らせ、心臓に戻すためには筋肉の力が必要です。
-
ふくらはぎのポンプ機能: 特に心臓から遠い足元は、ふくらはぎの筋肉が収縮することで血液やリンパ液を押し上げる「第二の心臓」の役割を担っています。
-
長時間の同一姿勢: デスクワークや立ち仕事などで長時間同じ姿勢を続けると、このポンプ機能が働かず、水分が重力で下半身に溜まりやすくなります。
3. 不適切な食習慣と水分補給
-
塩分(ナトリウム)の摂りすぎ: 味の濃い食事は、体内の水分を細胞間に引き寄せて溜め込むため、むくみの直接的な原因となります。
-
カリウムやミネラルの不足: 野菜や海藻類に豊富なカリウムは、余分な塩分(ナトリウム)の排出を助ける重要なミネラルです。これが不足すると、水分が体外に出にくくなります。
-
一度の大量摂取: 一度に大量の水を飲むと、体が処理しきれずに水が胃腸に停滞し、水滞を悪化させることがあります。
今すぐできる!余分な水をため込まないための対策
水滞を改善し、体の巡りを良くするには、「温める」「巡らせる」「出す」の3つを意識した習慣が重要です。
| 対策の柱 | 具体的な行動 | ポイント |
|---|---|---|
| 温める | 常温以上の飲み物を飲む | 白湯や温かいお茶(麦茶など)で内臓を冷やさない |
| 入浴で体を芯から温める | 湯船に浸かり、発汗を促すことで全身の巡りを改善 | |
| 腹巻きや靴下で冷えを防ぐ | お腹や足首など、水分代謝に関わる部位を温める | |
| 巡らせる | ふくらはぎを動かす | ウォーキングやスクワット、または座りながら足首を回す |
| 簡単なマッサージを取り入れる | ふくらはぎや足裏を揉みほぐし、リンパの流れを促進 | |
| 出す | 利水作用のある食材を摂る | きゅうり、冬瓜、小豆、海藻類、ハトムギ茶など |
| カリウム豊富な野菜を摂る | ほうれん草、芋類、果物などを摂り、塩分排出を促す |
「尿の出が悪くなる」ということは、体内に「余分な水分がたまる=滞る」ことを意味し、「気の滞り」(うつ)が「水の滞り」の原因になったという証拠でもあります。
新陳代謝を促すサイロキシンというホルモンを分泌する甲状腺の働きが低下して起こる粘液水腫(甲状腺機能低下症)は、体温が低下し、体のあらゆる代謝が滞るため、むくみ(水の滞り)、便秘、動作の不活発などの身体症状が現れます。その後、「やる気がしない」「計算したくない」といった「気」の流れの滞りの症状が出てくることもあります。
巷には「水を飲んでも、お茶を飲んでも太る」という人がいますが、これは漢方でいう色白水太りの陰性体質の肥満です。つまり、「水の滞り」からくる肥満ということになります。
このタイプの肥満の人は、体温が低下し、甲状腺機能低下症に似た病態を示すことがあります。そして、やはり「やる気がしない」「何となくだるい」「根気がない」と訴えることが多いです。こうした例は、「水の滞り」が「気の滞り」を引き起こすことを示しています。
心臓弁膜症や心筋梗塞などで心臓の力が低下し、全身の血流が悪くなる、つまり「血が滞る」と、やがて心不全に陥ります。すると、まず下肢からむくみはじめ、悪化すると肺や肝臓、胃腸などの内臓にも水が滞り、肺水腫やうっ血肝(肝腫大)を起こします。このことは、「血の滞り」が「水の滞り」を引き起こすことを示しています。
逆に、慢性腎炎や糖尿病性腎症などで腎不全にかかり、尿の出が悪くなって全身にむくみが出てくると、やがて心不全に陥ります。すると全身の血行が悪くなり、ひどくなると出血や血栓を起こすこともあります。これは、「水の滞り」が「血の滞り」を誘発したことを意味しています。
このように、あらゆる病気に「水の滞り」は関与しており、「気」や「血」とも深く関係しています。「水」は、人間の健康や病気に大きく関わっていることが分かります。