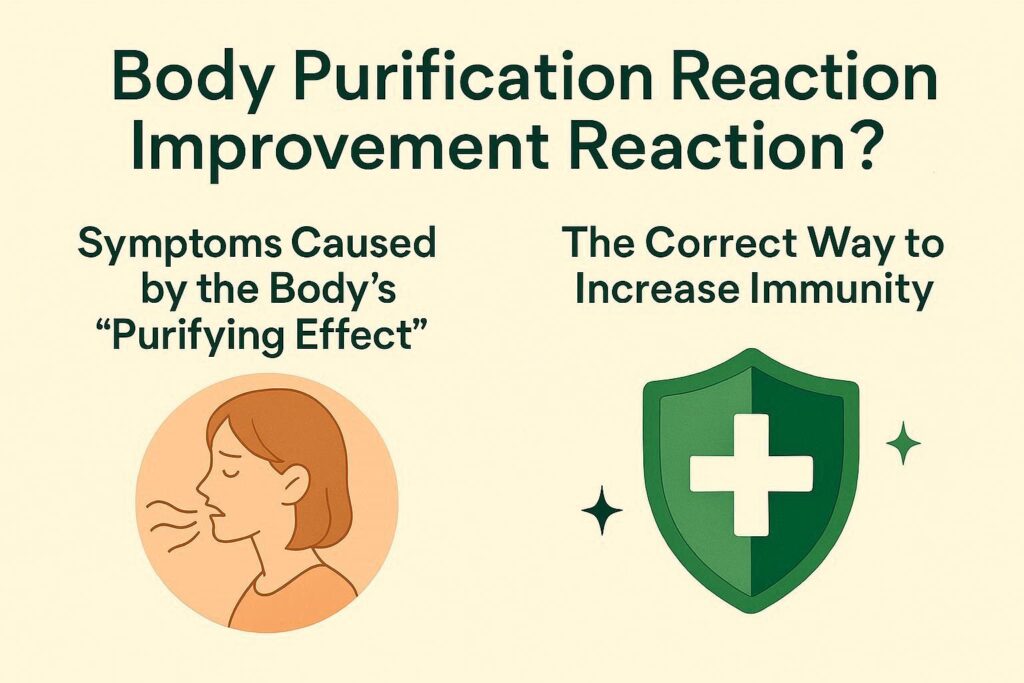体の浄化反応 好転反応? 体の「浄化作用」で起こる症状と免疫を上げる正しい対処法を紹介します。
健康的な生活習慣を始めたり、体質改善に取り組んだりした途端に、だるさ、発熱、湿疹、下痢といった一見「悪化」したような症状が現れることがあります。これは、体が溜め込んだ老廃物や毒素を排出しようとする浄化作用(デトックス)の表れかもしれません。東洋医学ではこれを「好転反応」と呼び、体が良い方向へ向かっているサインと捉えます。
体の浄化反応
しかし、この反応をただの体調不良と勘違いして途中で諦めてしまう人も少なくありません。本記事では、この好転反応が起こるメカニズムを解説し、免疫力向上と体質改善をスムーズに進めるために、浄化作用で起こる症状を正しく乗りこなし、効果を最大化するための具体的な対処法をご紹介します。
「血が滞る」と、手掌紅斑、くも状血管腫、下肢の静脈瘤、痔などのさまざまな他覚症状が現れるうえ、肩こり、頭痛、めまい、耳鳴り、動悸、息切れ、のぼせなど、多様な自覚症状も現れます。これらの自覚・他覚症状は、「血の滞り」が起きていることを示す警告反応であると同時に、その「滞り」を改善しようとする体の治癒反応でもあります。
しかし、この「血の滞り」による反応に対して適切な処理を行わないと、さまざまな病気が潜在することになります。
小川のせせらぎも、流れがせき止められるとやがてドブ川になるように、瘀血(「血の滞り」)も長く続くと血液中の成分の過不足が生じ、血液が汚れてきます。つまり、瘀血が汚血を作ることになるのです。
たとえば、糖や脂肪や尿酸の増加は、高血糖(糖尿病)、高脂血症、高尿酸血症(痛風)を引き起こし、赤血球の過剰は多血症(血栓症)を招きます。尿素窒素やクレアチニンなどの老廃物の増加は、それ自体が腎機能障害を意味します。
こうした栄養過剰物や老廃物の増加は、単に病名を引き起こすだけにとどまりません。汚血が全身の細胞に四六時中接することで、細胞を少しずつ傷めつけ、病気に追いやっていくのです。
たとえば、尿素窒素やクレアチニンが血液中に増加した腎不全の状態では、食欲不振や吐き気などの消化器症状に始まり、むくみ、高血圧、不整脈、うっ血性心不全、肺水腫などの呼吸・循環器症状、痙攣、意識障害、知覚・運動障害などの脳神経障害のほか、吐血や下血をはじめ、全身が出血傾向を示すこともあります(尿毒症)。
これは血液の汚れが極まったときの症状ですが、それほど汚れがなくても、汚血=瘀血は全身60兆個の細胞を薄い毒ガス室に閉じ込めたように少しずつ機能を麻痺させ、病気に追いやっていきます。
こうした瘀血=汚血から逃れるために、体はさまざまな反応を起こして汚血を浄化しようとします。以下に述べる症状は、実は体の浄血反応です。
発疹・吹き出物
「皮膚病の三ない」と言われるのは「わからない」「治らない」「死なない」の三つです。皮膚病で死ぬことはまずありませんが、原因がわからないことが多いため、治らないことも多いという意味です。
西洋医学では、皮膚病を皮膚に限った疾患と見なすため、蕁麻疹や湿疹などの皮膚の病気には抗ヒスタミン剤やステロイド剤、消炎剤を処方・塗布して発疹を止めようとします。
しかし、東洋医学では、発疹は瘀血=汚血を体表から外に出し、血液をきれいにしようとする反応です。そのため、治療では体外への発散を促し、血液中の老廃物を排出して治すことを重視します。
風邪薬で有名な葛根湯も、体を温めて発汗させ、老廃物を捨てる作用があります。そのため、肩や首がこり、汗があまり出ない人の皮膚病に効果があることもあります。
皮膚病は、大食であまり運動しない人に起こる傾向が強く、これは大食の人の血液が汚れやすいことを示しています。
炎症
肺炎、気管支炎、胆のう炎、膀胱炎など、「○○炎」とつく病気(炎症)が起こると、西洋医学では病原菌(細菌やウイルス)が原因と考え、抗生物質で殺菌しようとします。
しかし、細菌は汚れた場所にしか存在せず、小川や南洋のきれいな海にはほとんどいません。細菌は不要なものや死んだもの、余ったものを分解して土に戻す働きをするため存在します。つまり、体内で炎症が起こるのは血液が汚れているサインであり、血液の汚れを燃やすことで発熱します。また、血を汚す最大の原因は過食なので、炎症の間は食欲を抑えるようになり、これが食欲不振です。
動脈硬化・胆石・尿路結石
汚血の浄化反応である発疹や炎症を薬で抑えたり、加齢で発疹や発熱の力が低下すると、汚れた血液が全身の細胞に巡らないよう、血管内にコレステロールや中性脂肪、尿酸やピルビン酸などの老廃物を沈着させ、血流をサラサラに保とうとします。これが動脈硬化です。血管が狭くなるため、心臓は力を入れて血液を押し出し、高血圧となります。
高血圧に対して西洋医学は心臓の力を弱めるβ遮断薬や血管拡張剤を用いますが、同じ生活習慣を続けると血液がさらに汚れ、ドロドロになります。その結果、血液の流れを保つため血液の汚れが1か所に固まり、血栓ができます。
同様に、胆汁や尿の成分が濃すぎたり汚れて流れが悪くなると、その流れをサラサラに保つために、胆石や尿路結石ができます。胆汁や尿も元は血液なので、結石も「血の汚れ」が遠因と考えられます。
出血やガン
血栓や結石、動脈硬化などの原因が血液の汚れ(汚血=瘀血)だと気づかず、血栓溶解剤や血管拡張剤、手術などで対処すると、体は自然治癒力で血の汚れが全身の細胞に及ばないように、出血したり血液の汚れの塊(浄化装置)を作ろうとします。
鼻血、痔出血、胃潰瘍の吐血、脳出血、婦人性器からの不正出血などの出血は、すべて汚血の浄化反応です。
昔から瀉血療法(治療目的で静脈から血液を抜く療法)が行われてきたのも一理あります。女性は思春期より約35年間、月経による出血(自然の浄血)があり、28日周期で年間13回、1回の生理が約6日間とすると、6日×13回×35年=2730日となり、約7.5年間に相当します。男性の平均寿命78歳、女性の平均寿命85歳の7歳差は、一生の生理の日数で説明できるとも言えます。つまり、女性は生理で血液を浄化しており、そのぶん寿命も長いと考えられます。
ガン細胞も血液の汚れを浄化するために存在すると考える学者もいます。ガン腫瘍からは毒素が排出されており、ガン腫瘍は血液の汚れの浄化装置と考えても不自然ではありません。ガンの場合も、血痕(肺ガン)、吐血(胃ガン)、下血(大腸ガン)、不正出血(子宮ガン)、血尿(腎臓・膀胱ガン)など、必ず出血を伴います。