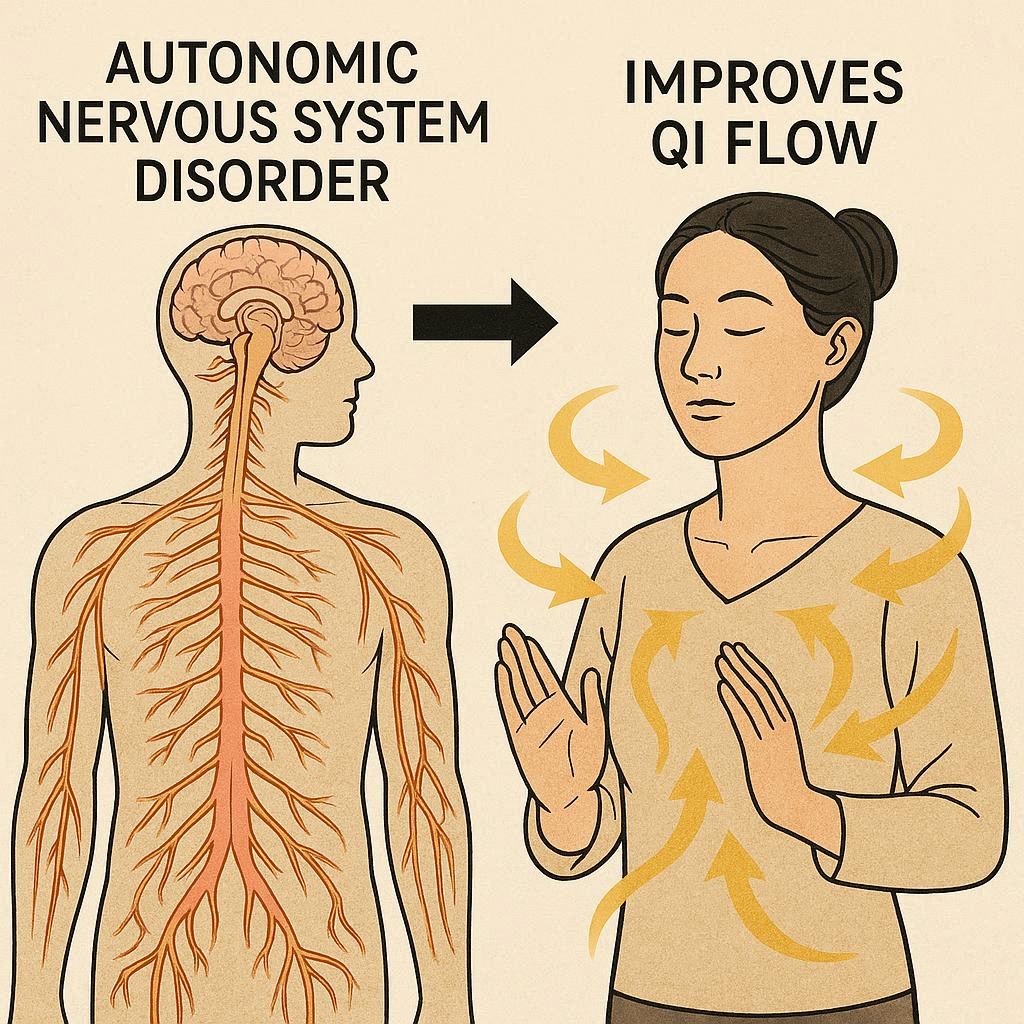自律神経失調症 気の流れを改善 することで遠ざけることができます。自律神経失調症も、漢方的にいうと「気の滞り」「気冷え」からくるので、先のうつ病の対策を1つでも多く実行することがとても大事です。
自律神経失調症 気の流れを改善
現代のストレス社会において、多様な心身の不調を引き起こす自律神経失調症は、東洋医学では**「気の流れの乱れ」として捉えられます。生命エネルギーである「気」が滞る「気滞(きたい)」や、上へ逆流する「気逆(きぎゃく)」は、不安感、動悸、めまい、そして不眠といった自律神経の乱れと深く結びついています。この「気の流れ」を根本から改善し、心身のバランスを取り戻すことは、自律神経失調症という不調を遠ざけ、再発を防ぐ**ための本質的なアプローチです。本記事では、この「気の流れ」をスムーズにし、安定した心と体を築くための具体的な漢方、食事、そして日々の養生法をご紹介します。
気の流れのタイプを理解する
自律神経失調症における「気の乱れ」は、主に以下のパターンに分けられます。
気滞(きたい):流れが滞る
- 状態: ストレスや精神的な緊張により、「気」の巡りが悪くなっている状態です。
- 症状: 抑うつ感、イライラ、胸や喉の圧迫感や違和感、ため息が多い、頭痛、腹部の張りなど。自律神経失調症の典型的な症状が多く含まれます。
気逆(きぎゃく):気が上衝する
- 状態: 気がスムーズに流れるべき下方向ではなく、上へ逆流している状態です。
- 症状: のぼせ、めまい、動悸、耳鳴り、頭がカーッとする、不眠など。パニック発作や強い不安感につながることもあります。
気虚(ききょ):気が不足する
- 状態: 過労や体力の消耗により、「気」のエネルギー自体が不足している状態です。
- 症状: 疲労感、倦怠感、食欲不振、少し動くとすぐ疲れる、気力が出ないなど。自律神経の働きを支えるエネルギーが不足している状態です。
気の流れを改善する具体的な方法
気滞や気逆を解消し、気虚を補うことで、自律神経のバランス回復を図ります。
漢方薬による改善
専門家(医師・薬剤師)に相談の上、体質に合った漢方薬を選ぶことで、乱れた気の流れを整えます。
- 気の滞り・イライラに:
- 加味逍遙散(かみしょうようさん):ストレスによる気滞を解消し、のぼせやイライラを緩和します。
- 柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう):強い不安、動悸、不眠など、高ぶった神経を鎮め、気の巡りを改善します。
- 半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう):喉のつかえ感(梅核気)や不安感など、気滞に伴う身体症状に用いられます。
- 気の不足による疲労に:
- 補中益気湯(ほちゅうえっきとう):低下した胃腸の働きを助け、気を補い、倦怠感や疲労を改善します。
食事と生活習慣の養生
1. 気を巡らせる(理気)
- 香りを利用する: 柑橘類(特に皮)、シソ、三つ葉、セロリ、ミントなどの香りの良い食材は、気の流れを促す作用があります。ハーブティーなどもおすすめです。
- 意識的な呼吸: 毎日数分間、ゆっくりと息を吐ききる腹式呼吸を行います。吐く息を長くすることで、体の緊張が緩み、気の滞りが解消されます。
- リラックス: ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる、軽いストレッチやヨガを行うなど、心身を緩める時間を作りましょう。
2. 気を補う(補気)
- 消化に良い食事: ご飯、芋類、豆類、きのこ類など、体を温め、消化吸収に負担がかからない食材を中心に摂り、胃腸の働きを助けましょう。
- 十分な休養: 過度な残業や夜更かしを避け、質の良い睡眠を確保することが、気の回復に最も重要です。
自律神経失調症の改善は、規則正しい生活と心の安定が鍵となります。漢方や養生法を日々の生活に取り入れ、ご自身のペースで気の流れを整えていきましょう。