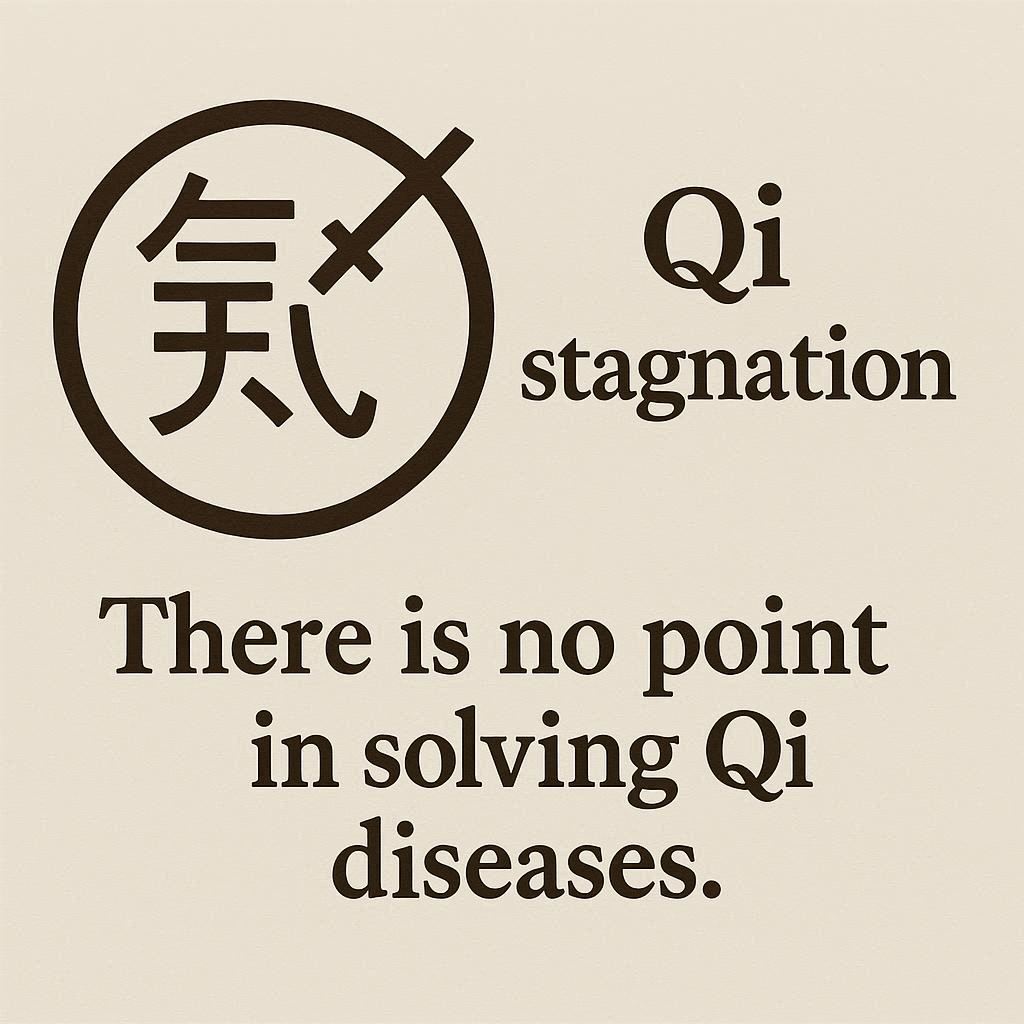気の滞り=気の病を解決しても意味がない 理由を紹介します。「気の滞り(気の病)」を解決するために、病気や人間だけを診るのでは不十分であるという考えは、東洋医学や伝統的な健康観の核心をついています。
これは、個人の体や心の状態だけでなく、それを包む「環境」と「社会」との関係性、つまり全体性(ホリスティックな視点)を重視するからです。
気の滞りを解決するために「人間と病気だけ」では不十分な理由
「気の滞り」は、単なる肉体的な不調や精神的な問題ではなく、エネルギーの流れが停滞している状態を指します。この停滞を解消するには、その原因が個人の中だけでなく、外部環境にあることを見極める必要があります。
1. 「環境」との関係性:自然界のエネルギーの影響
東洋医学では、人間の身体は自然界の縮図であり、外部の環境と常に相互作用していると考えます。
- 季節の変化(五季):
- 季節の変わり目は、急激な温度や湿度の変化により、身体がその変化についていけず、気の流れが乱れやすい時期です。例えば、梅雨の湿気(湿邪)は、消化器系の気の巡りを妨げやすいとされます。
- 対策には:治療家や医師は、患者の体質だけでなく、住んでいる地域の気候や季節を考慮に入れた生活指導が必要です。
- 住居・空間(風水):
- 住環境や仕事場の日当たり、風通し、清潔さは、その空間の気に影響し、結果としてそこにいる人の気に影響します。
- 対策には:身体の治療だけでなく、生活空間や寝室の環境改善(換気、整理整頓)といった指導も必要になります。
2. 「社会」との関係性:人間関係と感情の影響
気の乱れの最大の原因の一つは、人間関係や社会生活から生じる「七情(しちじょう)」と呼ばれる過度な感情の動きです。
- 七情の乱れ:
- 怒り、喜び、思い悩む、憂い、恐れなどの感情が過剰になったり、抑圧されたりすると、特定の臓器の気の流れに影響を与え、病気につながります。(例:怒りは肝の気を滞らせる)
- 対策には:患者の肉体の病気や症状だけを診るのではなく、職場や家庭内の人間関係、仕事の量や質など、ストレス源となっている社会環境を把握し、そこから距離をとる、あるいは関係性を改善するためのサポートが必要です。
- 生活リズムの乱れ:
- 現代社会の夜型生活、不規則な食事、過労などは、自律神経を乱し、気の生成や巡りを根本的に弱らせます。
- 対策には:薬や施術だけでなく、生活習慣の具体的な改善(睡眠時間、運動、食養生)という、患者の社会的な活動パターンに踏み込んだアプローチが欠かせません。
結論:「気」の病は全体(ホリスティック)から診る
「気の滞り」を解決するということは、身体の臓器や症状といったミクロな視点だけでなく、「人間 ↔ 環境 ↔ 社会」というマクロな相互作用の中で生じたバランスの崩れを整える作業です。
そのため、病気の原因を「個人の外」にある環境やストレス源にも求め、それらに対する対処法や生活様式の改善を提案することこそが、気の病を根本から解決するために不可欠となります。